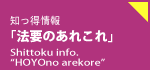お通夜や告別式の準備や進行は葬儀屋さんが殆どやってくれるので心配することはあまりないのですが、葬儀後の香典返しや法事・法要の時期は喪主・施主が決めることになります。またお通夜や告別式に参列される方々の香典も自分で準備しなければなりません。そんな時「知らなかった」では済まされないこともあるので参考にしていただけたらと思います。
香典金額の相場
| 関係 | 金額の相場 |
|---|---|
| 父母 | 50,000〜100,000円 |
| 兄弟姉妹 | 30,000〜50,000円 |
| 祖父母 | 15,000〜30,000円 |
| おじ・おば | 10,000〜20,000円 |
| その他の親戚 | 10,000〜30,000円 |
| 職場の上司 | 5,000〜10,000円 |
| 職場の同僚 | 5,000〜7,000円 |
| 職場の部下 | 10,000円 |
| 職場の家族 | 4,000〜5,000円 |
| 友人 | 5,000〜10,000円 |
| 隣近所 | 5,000〜7,000円 |
葬儀に参列する際に頭を抱えるのがお香典の金額ではないでしょうか。多すぎると喪主の方の負担になったり、少なすぎると非常識と思われたり。そんな時にも、とりあえずの目安となる金額を知っていると安心です。金額は年代が上がるにつれて若干上がる場合があります。ご自分の家庭で葬儀を行ったことがある方は、いただいたお香典の金額を参考にするのが望ましいでしょう。
こんな時のためにもシッカリと記録しておくことが大切です。
香典の郵送
都合によりどうしてもお通夜や告別式に参列できない場合、香典を郵送する方法があります。この時、現金を香典袋(不祝儀袋)に入れて現金書留で送りますが、故人を偲ぶメッセージ(お悔やみ文)を添えると良いでしょう。郵送する場合も持参する時と同じように書くことを忘れないようにして下さい。
香典の表書き
| 仏教 | 「御供養」 「御香料」 ※宗教が分かっている場合は、それに従うのが望ましい |
| 浄土真宗 | 「御仏前」 |
| 神式 | 「御神饌料」 「御玉串料」 |
| プロテスタント | 「お花料」 |
| カトリック | 「御ミサ料」 |
| 宗旨不明 | 「御霊前」 |
香典返しの名簿整理
香典返しは地域によって様々で、やらないところや一律で即返しをするところもあります。葬儀の際には弔問客の氏名、住所、電話番号、香典の金額を記録しておくと良いでしょう。香典返しのために金額別に分類しておくと便利です。これは香典返しで使用しなくても、参列者の方から訃報をいただいた時の香典の金額の参考にもなります。また花輪や生花、弔電をいただいた方も記録しておくと良いでしょう。
香典返しの「のし」の書き方
| 仏教 | 「忌明」、「満中陰志」など |
| プロテスタント | 「召天記念」、「感謝」 |
| カトリック | 「偲草」、「しのび草」など |
※宗派を問わず一般的に「志」が使われているようです。
香典返しの挨拶状
香典返しをする時は挨拶状を添えるのが望ましいです。特に即返しでない場合は、忌明けの会葬のお礼や四十九日の法要を済ませた旨を記載します。
香典返しの金額
一般的な例では、いただいたお香典の「半返し」と言われています。しかし「関東の半返し、関西の三分の一返し」などと謂われたように地域によって異なったり、ご家族の立場や故人の地位などによっても変わるので、一概にこれが正しいということはありません。しいて言うならば「三分の一」から「半分」となります。
| 香典金額 | 半返し | 4割返し | 3割返し |
|---|---|---|---|
| 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 5,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 10,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 30,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 50,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 100,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
香典返しの時期
一般的には忌明けの当日から1ヶ月以内となっています。地域によっては忌明けまでに3ヶ月かかる場合や年を越えてしまうような時などは、短縮して三十五日(五七日忌)をもって忌明けとするところもあります。また近年、葬儀後や初七日の時に香典返しを行う略式での即返しが増えています。即返しの場合はいただいたお香典の額に関係なく一律となります。そのため即返しの場合でも高額なお香典をいただいた時は、後日挨拶状を添えて正式に香典返しをすることが望ましいです。
神式の場合は三十日祭または五十日祭の後に行います。
キリスト教式では特に決まっていませんが、1ヵ月後の追悼ミサや召天記念式後に行う方が多いようです。
| 県別 | 忌明け | 時期 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||
| 北海道 | 七七日 | 習慣なし (本州の親族にのみ行う場合がある) |
粗供養品 (300~500円程度) |
| 青森 | 七七日/五七日 /三七日 |
即返し | 会葬礼品に近い |
| 岩手 | 五七日 | 即返し | 会葬礼品に近い |
| 秋田 | 即返し | ||
| 山形 | 七七日 | 即返し | 会葬礼品に近い |
| 宮城 | 即返し | 会葬礼品に近い | |
| 福島 | 七七日 | 即返し(告別式後) | 会葬礼品に近い |
| 関東 | |||
| 茨城 | 七七日/一年目 | 即返し | |
| 栃木 | 即返し | ||
| 群馬 | 七七日 | 即返し | 3,000〜5,000円 |
| 千葉 | 即返し | ||
| 埼玉 | 七七日 | 即返し (一部地域で忌明け) |
|
| 東京 | 七七日 | 忌明け | |
| 神奈川 | 七七日 | 即返し (横浜など一部地域で忌明け) |
|
| 北陸・甲信越 | |||
| 山梨 | 七七日 | 即返し | |
| 長野 | 七七日 | 即返し | 2,000円程度 |
| 新潟 | 葬儀後2週間前後 | ||
| 富山 | 即返し | ||
| 石川 | 男性:七七日 女性:五七日 |
即返し | |
| 福井 | 男性:七七日 女性:五七日 |
即返し | |
| 東海・近畿 | |||
| 静岡 | 七七日/五七日 | 忌明け/即返し | |
| 愛知 | 忌明け | ||
| 岐阜 | 忌明け | ||
| 三重 | 七七日/五七日 | 忌明け | |
| 滋賀 | 七七日 | 忌明け (彦根付近は即返し) |
|
| 京都 | 五七日 (本来は七七日) |
忌明け | 市内は会葬礼品に商品券を使用 |
| 奈良 | 忌明け | ||
| 和歌山 | 忌明け | ||
| 大阪 | 七七日 | 忌明け | |
| 兵庫 | 七七日 | 忌明け | 半返し |
| 中国・四国 | |||
| 鳥取 | 七七日 | 即返し (鳥取市は忌明け) |
|
| 島根 | 即返し | ||
| 岡山 | 即返し | ||
| 広島 | 七七日/五七日 | ||
| 山口 | 忌明け | ||
| 徳島 | 忌明け | ||
| 香川 | 忌明け | ||
| 愛媛 | 忌明け | 半返し | |
| 高知 | 即返し | ||
| 九州・沖縄 | |||
| 福岡 | 忌明けまで | ||
| 佐賀 | 七七日 | 初七日/忌明けまで | |
| 長崎 | 忌明けまで | ||
| 熊本 | 忌明けまで | ||
| 大分 | 七七日 | 忌明け | 半返し |
| 宮崎 | |||
| 鹿児島 | 七七日 | ||
| 沖縄 | |||
即返しの場合でも受付時に香典と引き換えに香典返しをする場合と、帰りに引換券と引き換えに渡す場合があります。香典返しをいただく立場から考えると、帰りに引換券と引き換えに香典返しをいただいたほうが都合が良いです。と言うのも、先にいただくと荷物が多くなってしまい焼香時などに困ってしまうからです。立ち席の場合は本当に困るものです。
引き出物の「のし」の書き方
| 仏教 | 「供養志」、「粗供養」 |
| カトリック | 「昇天記念」 |
| プロテスタント | 「召天記念」 |
引き出物の金額の目安
2,000~5,000円程度で参列者全員に配るのが一般的です。
法事・法要の種類
| 名称 | 時期 | 説明 |
|---|---|---|
| 通夜 | 地域によっては通夜とは別に本通夜を行うところもある | |
| 告別式 | ||
| 三日参り | 九州地方でみられる | |
| 初七日法要 | 死後7日目 | 告別式当日に繰上法要とされる場合が多い |
| 二七日法要 | 死後14日目 | |
| 三七日法要 | 死後21日目 | |
| 四七日法要 | 死後28日目 | |
| 五七日法要 | 死後35日目 | |
| 六七日法要 | 死後42日目 | |
| 七七日法要 | 死後49日目 | 一般に四十九日と言う |
| 百ヶ日法要 | 死後100日目 | |
| 一周忌 | 死後1年目 | |
| 三回忌 | 死後2年目 | 亡くなった年を1と数える |
| 七回忌 | 死後6年目 | |
| 十三回忌 | 死後12年目 | |
| 十七回忌 | 死後16年目 | |
| 二十三回忌 | 死後22年目 | |
| 二十七回忌 | 死後26年目 | |
| 三十三回忌 | 死後32年目 | 三十三回忌の年忌法要を持って永代供養とすることが多い |
| 三十七回忌 | 死後36年目 | |
| 五十回忌 | 死後49年目 | 通常、本当に最後の年忌止めとなる |